
薄暗い部屋の中で、私は混乱していた。
先日まで普通に生活していたはずなのに、気がつけば自分が猫の体に閉じ込められていた。
目の前には彼女――告白されたあの瞬間から何かが変わってしまったのだと感じる、振ったばかりの彼女がいた。
「どうして、僕がこんなことに?」
声は出ない。喉を震わせても、ただの猫の鳴き声しか発せられない。
頭の中は混乱し、どうやって元に戻ればいいのかすら分からない。
体を動かすたび、猫の感覚が押し寄せてくる。
しなやかな四肢、鋭い爪、柔らかな毛――すべてが今の自分の体の一部なのだ。
彼女は私を撫でながら、優しい目をして微笑んでいた。
「ミケ、どう?慣れた?」
彼女の声は甘く、まるで私が本当にミケであるかのように話しかけてくる。
私が振り返ると、彼女の膝の上に座っているのは、彼の姿をした何か――いや、ミケの魂を宿した存在だった。
どうやら彼とミケが入れ替わってしまったらしい。
「どうして…?どうしてこんなことになったんだ?」
私は焦り、彼女に訴えかけようとするが、やはり猫の鳴き声しか出ない。彼女は私の声に耳を傾ける素振りを見せたが、私の意図を理解する様子はなかった。
――何とか元に戻らなければ。そう思い、家中を歩き回って解決策を探し続けた。
しかし、どれだけ考えても答えは出ない。
体が猫になってしまった今、人間のように物を扱うことはできないし、言葉を発することもできない。
どんなに焦っても、その現実が重くのしかかってくるだけだった。
数週間が経過するにつれ、彼女との日常が少しずつ形作られていった。
彼女は相変わらず私を「ミケ」として可愛がり、まるで昔からの飼い猫であるかのように接してくる。
時折、元の自分に戻る方法を考え、何とか彼女に真実を伝えようと試みるが、どうしても伝わらない。
そして、ある日、私はようやく気づいた。彼女はすでにすべてを知っていたのだ。
彼女が猫と私を入れ替えたことに。そして、それを戻すつもりはないということに。
「あなたには、猫の方が似合ってるわ」
彼女のその言葉に、私は打ちひしがれた。
どうやら彼女は、振られた悔しさからこの状況を生み出したのだ。
だが、それでも彼女は私を大切にし、愛情を注いでくれている。
人としてではなく、猫として――だが、確かにそこには彼女の愛があった。
一方で、ミケは私の体の中で次第に彼女の生活に順応していった。
彼女のそばで寄り添い、時には彼女の頼もしいパートナーのように振る舞っていた。
彼の中にいるミケは、彼女の願いを理解していたのだろう。
そして、彼は彼女のために「彼」としての役割を果たすことを選んだのだ。
私は次第に、その事実を受け入れざるを得なくなった。
彼女の元で、猫として生きていくことが最善だと理解するようになった。
元に戻る方法を見つけることはできず、時間が経つにつれて、その希望も薄れていった。
――それでも、彼女のそばにいることができるなら。
そう思ったとき、私は自分の中にある小さな満足感に気づいた。
人としてではなくても、彼女と共に過ごす日々は決して悪いものではない。
彼女は私を撫で、優しく抱きしめてくれる。
そして、私もその愛情に応え、彼女の膝の上で安心感を感じるようになっていた。
「ミケ、ありがとう。あなたがいてくれて、本当に良かった」
彼女のその言葉に、私は静かに目を閉じた。
これが、私の新しい人生なのだ。彼女のそばで、猫として彼女を見守り続ける。
それが私の選んだ道だった。
その後、彼女と私―いや、彼女とミケは穏やかな日々を送っている。
彼の体に宿ったミケは、彼女の隣で人間としての役割を果たし、私は彼女の飼い猫として彼女を支え続けている。
夜、彼女の膝の上で丸くなるたびに、私は感じる。これで良かったのだと。

誰かに養ってもらって生きていきたい。
実際は家族を養う立場ですが
でも不満はあれど、これはこれで満足感あります。
でもいずれは仕事しないでレトロゲームをまったりやりながら生きていきたい。
そんな野望も持ちつつ、駄文を書きながら生きていきます。
相方や子どもには楽しく生きていってほしい。。。

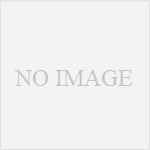

コメント