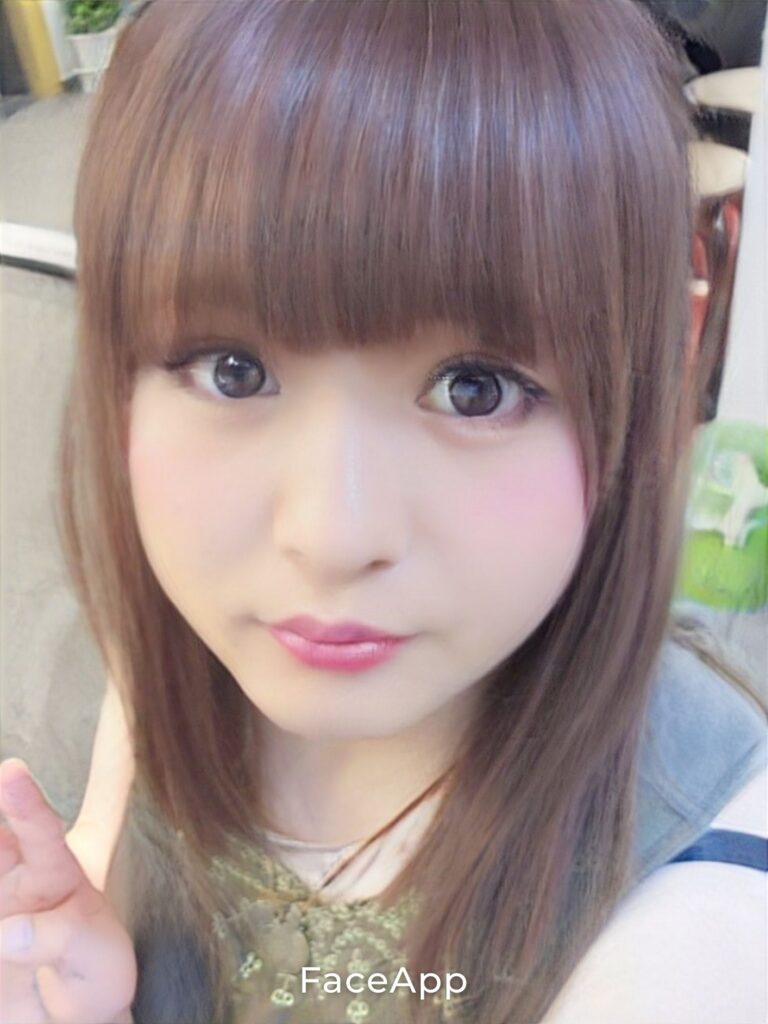
蒸し暑い夏の昼下がり、カーテンの隙間から差し込む光が、部屋の床に四角い光の塊を作っていた。
窓を開けると、熱気を帯びた生ぬるい風がそっと頬を撫でる。
梅雨が明けてからというもの、太陽の気まぐれな熱波がアスファルトを焼き、町全体が巨大なオーブンのようだった。
蓮(れん)は鏡の前に立ち、今日の“自分”を作り上げていく。
Tシャツにデニムという選択肢は、この部屋を出る瞬間にはもう頭の中にはない。
クローゼットの奥から取り出したのは、薄手のノースリーブワンピース。
鮮やかなレモンイエローが、夏の光を跳ね返して眩しい。
ふわりと広がるAラインが、風になびくたびに涼しげな錯覚を生む。
「今日の私は、どこまで自然に見えるだろう?」
それが、蓮のささやかな挑戦だった。
性別という枠組みを軽々と飛び越え、自分が最も心地よくいられる姿を追求すること。
それは、一種の芸術であり、終わりのない実験でもあった。
メイクポーチを開ける。
まずは、肌の色を均一にするための下地。
次に、ほんのりピンクがかったファンデーションを指で丁寧になじませる。
シミや毛穴を隠すというよりも、肌の透明感を増すための儀式だ。
眉は元の形を活かしつつ、少しだけ細く、優しく描く。
アイラインは跳ね上げず、目の形に沿って自然に。
そして、マスカラは重ね塗りをしない。
まつげ一本一本がすっと伸びた、清潔感のある仕上がりを目指す。
一番のポイントは、リップだ。
今日のワンピースに合わせて、コーラルピンクのグロスをたっぷり乗せる。
鏡の中で唇がきらりと光るたびに、蓮は自分が描く理想の像に一歩ずつ近づいていくのを感じた。
ウィッグを被る。
人毛に近い自然な質感の、鎖骨にかかるボブスタイル。
内巻きにセットされた毛先が、顔の輪郭をふんわりと包み込む。
ウィッグのネットを被り、ピンで地毛をしっかりと固定する。
この瞬間が、最も緊張する。
頭の中に「バレたらどうしよう」「変だと思われたらどうしよう」というささやきが生まれるが、それらを振り払うように、ウィッグをそっと頭に乗せる。
鏡の中の「蓮」は、もう元の姿ではない。
そこにいるのは、レモンイエローのワンピースを着た、涼しげな表情の「誰か」だ。
「よし、完璧」
心の中で小さく呟き、満足げに微笑む。
部屋を出る前に、全身鏡の前でくるりと一回転。
ふわりと舞うスカートの裾が、心地よい高揚感をもたらした。
街へ繰り出す前の、このわずかな緊張と高揚感が、蓮にとっては何よりも特別だった。
蓮が待ち合わせのカフェに足を踏み入れると、エアコンの冷気がふわりと頬を撫でた。
店内は、日曜の昼下がりということもあり、適度な賑わいを見せている。
窓際の席に目をやると、見慣れた顔がスマホをいじりながら、グラスの水を飲んでいた。
「翔太、ごめん、待った?」
蓮が声をかけると、翔太(しょうた)は顔を上げてにこりと笑った。
「おう、遅ぇよ。って、お前、また随分可愛らしい格好で来たな」
翔太は、蓮の女装癖を唯一知っている親友だ。
中学からの付き合いで、男らしくて飾らない性格の彼とは、何を話しても気が楽だった。
最初に女装姿を見せた時は、さすがに驚かれたが、「お前が好きなんなら、別にいいんじゃね?」とあっさり受け入れてくれた。
その時、蓮は心の底から安堵したのを覚えている。
蓮は空いている椅子を引き、翔太の向かいに座った。
「可愛らしい、とか言うなよ。……はいはい、新作の服見せに来たんだから、褒めてよ」
蓮が冗談めかして言うと、翔太はグラスをテーブルに置き、じっと蓮の姿を観察した。
「なんかさ、今日のは特に、いつもと違うな。えっと……色?」
「んー、色もそうだけど、シルエットもかな。Aラインは初めて挑戦してみた」
「ふーん。似合ってるじゃん。正直、下手な女より似合うわ」
「それ、褒め言葉になってる?」
蓮は笑いながらメニューを開いた。
しかし、翔太は何か言いたげに、蓮の肩のあたりをじっと見つめている。
「……なあ、蓮」
「なに? 注文決まった?」
「いや、その……肩のとこ、見えてるぞ」
翔太が指差すのは、蓮の左肩だった。
ノースリーブのワンピースから、肩紐が少しだけはみ出している。
蓮は一瞬、心臓が止まるかと思った。
まさか、ブラジャーの肩紐が見えていたなんて。
動揺を隠すように、蓮はわざと明るい声で返した。
「え、まさか興奮してる? 女装男子のブラ紐なんかで」
蓮の言葉に、翔太は目を丸くして慌てて否定した。
「するかよ! いや、そういうんじゃなくて! 見えてるよ、って、ただ言いたかっただけで……」
しかし、彼の顔は耳まで真っ赤になっていた。
その様子がなんだかおかしくて、蓮は思わずくすりと笑ってしまった。
(指摘してくれるのはありがたい。でも……その反応、ちょっと可愛い)
自分たちだけの「秘密」を共有しているという空気が、二人の間に流れる。
この小さなハプニングが、今日の会話を特別なものにする予感がした。
蓮は左肩の肩紐をそっと直しながら、翔太に尋ねた。
「でもさ、本当に興奮したんじゃないの?」
蓮のからかいに、翔太はますます顔を赤くして反論する。
「するかよ! 馬鹿。でも、その……確かに、ちょっとドキッとしたのは認める」
「え、なんで?」
「いや、なんでって……その、お前がいつもより、なんだか色っぽく見えたっていうか……」
言葉を濁しながらも、翔太は蓮から目をそらさない。
その真剣な眼差しに、蓮の胸は小さく跳ねた。
「それ、褒めてるんだよね? ありがとう」
蓮は少し照れくさそうに笑いながら、目の前のカフェラテに口をつけた。
(翔太はただの友達?それとも……?)
蓮の女装をからかいつつも、いつも受け入れてくれる翔太。
その言葉の奥に隠された「本心」が、今日は少しだけ顔を覗かせた気がした。
ふと、蓮は周囲の視線が気になった。
カフェの他の客が、自分たちの方を見ているような気がする。
もしかしたら、自分の女装がバレているのかもしれない。
居心地の悪さを感じて、そっと身を固くした。
そんな蓮の様子に気づいたのか、翔太が優しく言った。
「大丈夫だよ。誰も気づいてないって。つーか、お前がそれだけ『自然』に見えてるってことだろ」
その言葉に、蓮は安心した。
翔太が隣にいるだけで、こんなにも心強い。
「ありがとう。……でも、翔太がそうやって庇ってくれると、ますます男らしくてかっこいいって思っちゃうな」
「は、なに言ってんだよ、急に。きもいって」
翔太は再び顔を赤くして、そっぽを向いた。
その横顔に、蓮は小さなやきもちのようなニュアンスを感じ取った。
まるで、自分にしか見せない表情を見ているような、特別な気分だった。
カフェでの会話が一段落した頃、蓮はいたずらっぽく翔太に微笑んだ。
「ねえ、翔太。今日の私、何かいつもと違うって言ったでしょ?」
「ああ、言ったな。えっと、色と、Aラインってやつだろ?」
「それだけじゃないの。実はね、今日の私には、特別な『ヒント』が隠されてるんだ。それが何か、当ててみてよ」
翔太はきょとんとした表情で蓮を見た。
「は? ヒント? なんだそれ」
「うーん、そうだなぁ。じゃあ、ヒント1:今日、私が家を出る前にしたこと。ヒント2:カフェに入る前に、私が一番気を使ったこと。この2つを合わせて考えてみて」
翔太は腕組みをして考え込む。
「家を出る前……? いや、そんなのわかんねぇよ。カフェに入る前に気を使ったこと……? いや、ますますわかんねぇな」
「ふふ、じゃあもう一つヒント。ヒント3:私にとって、夏に欠かせないもの」
「夏に欠かせないもの……?」
翔太は首を傾げた。
そして、蓮の姿をもう一度、じっくりと観察し始める。
レモンイエローのワンピース、鎖骨にかかるボブのウィッグ、ナチュラルメイク。
手には、小さなカゴバッグ。
足元は、白いサンダル。一体、どこに「ヒント」が隠されているのだろうか。
「……なあ、わかんねぇよ、これ。答え教えてくれ」
翔太は降参したように両手を上げた。
蓮はにやりと笑い、ゆっくりと答えを口にする。
「答えはね、『香り』だよ」
「香り?」
「そう。ヒント1の『家を出る前にしたこと』は、夏用の香水をつけたこと。ヒント2の『カフェに入る前に気を使ったこと』は、その香りが強すぎないか確認したこと。そして、ヒント3の『夏に欠かせないもの』は、汗をかいても香りが持続する、涼しげなシトラス系の香りだったんだ」
「……はぁ? そんなの分かるわけねぇだろ!」
「ふふ、でも、それが今日の私の『特別なヒント』。ね? 翔太は、いつもと違う私に、無意識にでも気が付いてくれたってことだよね?」
蓮はそう言って、再びからかうように微笑んだ。
翔太は頬を膨らませて、どこか悔しそうな表情を浮かべる。
「……ずるいぞ、お前。そんなの、分かるわけねぇだろ」
そのやりとりは、いつもの二人の距離感を物語っていた。
軽口を叩き合いながらも、お互いの存在を確かめ合っているような、そんな温かい時間だった。
カフェを出ると、夏の熱気が再び二人を包み込んだ。
アスファルトからは陽炎が立ち上り、通りを行き交う人々の影が細く伸びている。
「なあ、この後どうする? 買い物付き合ってくれないか?」
翔太が提案した。蓮は少し意外に思いながらも、嬉しくなって頷く。
「もちろん! どこ行く?」
「この先のショッピングモール。ちょっと、新しいスニーカーが欲しくてさ」
翔太に続いて、蓮はゆっくりと歩き出した。
並んで歩くのは、中学時代から変わらない。
部活帰り、塾帰り、いつもこんな風に、隣に翔太がいた。
ただ一つ違うのは、隣にいる蓮が、男の姿ではないことだけだ。
ショッピングモールに到着すると、二人はまずスニーカーショップに向かった。
翔太は真剣な表情で、いくつものスニーカーを手に取っては、鏡の前で履き心地を確かめている。
そんな彼の横顔を、蓮はぼんやりと眺めていた。
(翔太も、変わらないなぁ)
男友達といるのに、こんなにも居心地がいいのはなぜだろう。
それはきっと、翔太が蓮のありのままを、全て受け入れてくれているからだ。
翔太がスニーカーを選んでいる間、蓮は隣の洋服店に足を踏み入れた。
ウィンドーに飾られた、涼しげなリネン素材のワンピースに目が留まる。
「ねえ、翔太。ちょっとこれ、試着してきてもいい?」
翔太が頷くと、蓮はそのワンピースを手に取り、試着室に入った。
鏡の前で、レモンイエローのワンピースを脱ぎ、リネン素材の淡い水色のワンピースに袖を通す。
「どうかな?」
蓮が試着室から顔を出すと、翔太はスマホをいじるのをやめ、じっと蓮の姿を見つめた。
「……似合うじゃん。なんか、爽やかでいいな」
翔太は少し照れたように、目をそらした。
「本当に? 似合ってる? 変じゃない?」
蓮が念を押すと、翔太は真剣な表情で頷いた。
「変じゃない。むしろ、さっきのより大人っぽく見えるかも」
蓮は嬉しくなって、そのワンピースを脱ぎ、元のワンピースに着替えた。
再び試着室のドアを開け、出てきたその瞬間、翔太の視線が蓮の左肩に釘付けになる。
「……あ、まただ」
翔太は蓮の言葉を待たずに、手を伸ばした。
蓮の肩に触れるか触れないか、というところで、器用にブラジャーの肩紐をそっと直す。
その指先が、わずかに蓮の肌に触れた。
その一瞬、蓮は心臓が跳ねるのを感じた。
(今のはただの自然な仕草?それとも――)
翔太の指先から伝わってくる熱が、蓮の肌をじりじりと焼く。
ただの友達なら、こんな風に触れてくるだろうか。
そんな疑問が、蓮の頭の中を駆け巡った。

夏は女装すると涼しげなんですが
汗でメイク落ちるし、色々ケアも大変。
ガンガン身体を冷やしてから出かけてもあんまり効果ないですね。
出かけたい時期は夏ですが、出かけやすいのは秋ですね。
もう9月なのに涼しくならないな。。。




コメント