
「どうしても一度でいいから、おしゃれなカフェに行ってみたいんだ!」
その頼みをしたのは、俺——ヒロキ。
目の前にいるのは、俺の幼なじみのミカだ。
彼女は普段からおしゃれな店や可愛い服に興味がないタイプで、むしろ俺の方がそういう場所に憧れていた。
しかし、男一人ではさすがに勇気が出なくて、ずっと躊躇していたのだ。
「ほんとにそれだけ? 他に目的とか、変なことしないでよね?」
ミカは少し疑わしそうに俺を見つめたが、俺はすぐに首を振って誤魔化した。
「もちろん! ミカの代わりに、ちょっとその…体験してみたいだけだからさ!」
俺の言葉にミカはため息をつき、やれやれといった表情を浮かべながら小さく肩をすくめた。
「いいけど、後でちゃんと報告してね。変なことしたらすぐに戻ってもらうから。」
こうして俺たちはお互いの体を入れ替えることになった。
ミカが持っていた、不思議な力を使って。
最初は冗談かと思っていたけれど、彼女が本気でこの力を使うことを了承してくれたことに驚いた。
目の前の鏡に映るのは、ミカの姿。
黒髪をきれいにまとめ、薄いメイクを施している彼女の顔が、自分の顔になっていることがまだ信じられない。
「よし…行くか。」
ミカの体で初めて入るカフェ。
店内は思っていたよりも広く、光が優しく差し込んでいた。
店員もおしゃれで落ち着いた雰囲気だ。
正直、男の自分だったら絶対にここには来られなかっただろうなと思う。
俺は内心の興奮を抑えながら、ふと自分の手元に視線を向けた。
「この体で…ちゃんとできるかな。」
軽く震える手を眺め、カフェのメニューに目を通す。
ミカが好きそうなものを選びながら、スマホを取り出した。
「楽しんでる様子、ちゃんと送らないとな…。」
俺はメッセージアプリを開いて、ミカに写真を送る準備を始めた。
彼女が心配しているのはわかっていたし、後で説明をするつもりだったけれど、今はこの瞬間を楽しみたい。
カフェラテを頼み、スイーツも注文した。
普段なら絶対に選ばないようなメニューだが、今はミカの体を借りているので、彼女の趣味に合わせた選択をした。
「写真撮っとこうかな…」目の前に運ばれてきた綺麗なラテアートに、思わずスマホを取り出して写真を撮る。
白い泡の上に描かれたハートが、なんとも可愛らしい。
俺はその写真をミカに送った。
『見て、カフェラテ頼んだよ!』すぐに返信が返ってきた。
『変なことしてないでしょうね?』「…うーん、まあこれくらいは普通だろ。」
俺は小さく笑い、店内を見渡した。
どの席もおしゃれな若い女性たちで埋め尽くされている。
俺もその一員として違和感なく過ごしていることに、少しずつ慣れてきた。
一方、ミカはヒロキの部屋で、一人静かに笑みを浮かべていた。
彼女もまた、入れ替わりの体験を楽しんでいたのだ。
「ふふ、やっぱり男の体って自由な感じがするね…。」
ミカはヒロキの服装に少し興味を持ち、クローゼットを開けてみた。
そこには、彼の普段着がずらりと並んでいる。
「これ、似合うかな?」彼女は少し大胆に、ヒロキの少しだぼっとしたジャケットを羽織ってみる。
鏡に映る自分の姿に満足そうな顔を浮かべ、ポーズを取る。
普段の自分とは違う体験に、思わずウキウキしてしまった。
「へえ、これが男のジャケットか…。意外とカッコいいかも?」そのままジャケットを着たまま、彼のベッドに座り、ゲーム機を手に取った。
ヒロキがいつも遊んでいるゲームだ。
ミカは普段ゲームをしないタイプだったが、この体では何でもできる気がしてきた。
「こうやって遊んでるんだ、男の子って。」コントローラーを握りしめ、少しの間夢中になってゲームを楽しんだ。
ヒロキの部屋はシンプルで、男子らしい空気が漂っているが、ミカはその空間が不思議と心地よく感じられた。
「…意外といいかも。」彼女はふと、ヒロキの身体を使ってさらに楽しいことができないかと考えた。
「そうだ、今度は外に出てみようかな?」その考えに彼女は自分でも驚いた。
普段の自分なら、男の体で外に出るなんて思いもしないことだ。
しかし、今はヒロキの体だからこそ、できることがたくさんある。
その頃、ヒロキはカフェを出て、楽しげな気分で帰路に就いていた。
風が頬を撫でる感覚も、ミカの体だと少し違って感じる。
そして、彼はふとスマホを確認した。ミカからのメッセージが届いている。
『ねえ、君の部屋でゲームしてたら楽しくてつい遊んじゃった。』
「えっ、マジで?」ヒロキは驚きながらメッセージを読み進めた。
『今から外に出てみようかなって思ってるんだけど、何かリクエストある?』
「待て待て、俺の体で外に出るなんて…!」
俺は急いで返信を打つ。『勝手に外に出るなよ! 何かあったらどうするんだ!』
しかし、ミカからの返信は簡潔だった。『大丈夫、大丈夫。気をつけるから。それに、君も楽しんでるんでしょ?』
確かに、俺もミカの体でカフェを楽しんでいた。
彼女も俺の体で同じように自由を感じているのかもしれない。
「まあ、俺もさっき自撮りして楽しんでたし、文句は言えないか…。」俺は諦めの気持ちを抱きつつ、彼女が無茶をしないことを祈った。
その後、ミカはヒロキの体で街を歩き、彼の視点で見る世界を堪能した。
普段と違う身長、力強い体、そして周りから向けられる視線も全く違って感じた。
「男の体って、こんなに楽しいんだ。」彼女は笑顔を浮かべ、街を歩き続けた。

スイーツとかの店だったら男一人だと入りづらいかも?
でもこんなお願いを聞いてくれる仲なら、誘って一緒に行けばよいのでは?
というツッコミはこの手の話を書く際のご都合主義からくるものなのでスルーで。
イラストのスマホを持つ手が凄いことになってますね。。。

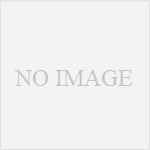
コメント