
秋風が吹き始め、少し肌寒くなった午後。
俺、三谷悠太(みたにゆうた)は、友人の七海(ななみ)に呼び出され、彼女のカフェの常連たちが集まる場所に来ていた。
彼女は昔からロリータファッションが大好きで、いつも自分の理想の写真を撮ろうと頑張っている。
しかし、今日は少し違う雰囲気を感じ取っていた。
「悠太、今日はお願いがあるの」
七海はいつもよりも真剣な表情で、俺に切り出した。
俺は彼女のその表情に一瞬驚いたが、何か企んでいるのではと予感がした。
「何?また撮影の手伝い?」
「うん、でもちょっとだけ違うの。私じゃなくて…あなたを撮りたいの」
「は?」
突然の申し出に、俺は目を見張った。七海は続けた。
「思った通りの写真が撮れなくてさ…被写体になるとポーズとか気にしすぎちゃって、自然な感じが出せないんだ。それでね、ちょっとアイデアがあって…」
「いやいや、俺を被写体にするって…」
七海の目は、まるで全てを見透かすように輝いていた。
「大丈夫。ちょっと特殊な方法を使うから…入れ替わろう」
「え?」
その瞬間、彼女が笑みを浮かべた。次の瞬間、目の前が真っ白になり、俺の意識は遠のいた。
目を開けると、目の前に見慣れた自分の顔があった。
それも、自分自身を見上げる角度で。
「嘘だろ…」
声も違う。高くて、柔らかい。俺は両手を見下ろし、細くて小さな指先を確認する。
そして、目の前に立つ「俺」も、驚きと戸惑いが入り混じった表情を浮かべていた。
「入れ替わったって、本当に…?」
七海の声が聞こえたが、それは俺の口から発せられていた。
どうやら彼女の言う通り、俺たちは身体を入れ替えてしまったようだ。
「大丈夫、悠太。この体験を通して、きっといい写真が撮れるから」
七海は俺の体を操作しながら言った。
俺はまだ状況が飲み込めていなかったが、彼女の信念には圧倒されるばかりだった。
彼女の部屋に着くと、七海のロリータ衣装が準備されていた。
フリルやリボン、繊細なレースに包まれたドレスが、俺の目の前に並んでいる。
「え、これ着るの…?」
俺が戸惑っていると、七海はにやりと笑って言った。
「そう、これを着て、ポーズを決めてもらうの。大丈夫、慣れれば楽しくなるから」
内心、楽しくなんてなれるわけがないと思いながらも、彼女に押し切られ、俺は仕方なくドレスに袖を通すことにした。
想像以上に重たくて、動きにくい。
「これ、よく着てるな…」
「慣れれば問題ないわよ。さ、ポーズはこう。腰を少し斜めにして、手は顔の近くでVサイン。あと、表情はもう少し柔らかくして」
彼女の細かい指示が飛ぶ。
俺は初めてのロリータファッションに戸惑いながら、なんとか彼女の要求に応えようと頑張るが、うまくいかない。
「違う、もっと自然に!こう!」
彼女は俺の体を使って、理想的なポーズを見せてくる。
そのたびに、俺は内心で焦る。
「…難しいな、これ」
しかし、撮影が進むにつれ、少しずつ俺も慣れてきた。
七海の指示に従い、ポーズを取り続けるうちに、なんだか不思議な気分になっていく。
ロリータファッションを着ている自分の姿が、レンズ越しに少しずつ馴染んでいくのを感じ始めた。
撮影が終わると、七海は満足げにカメラをチェックしていた。
彼女は目を輝かせながら、俺に言った。
「悠太、すごく良かったよ。これならきっと素敵な写真になる!」
俺は疲れ果てていたが、彼女の笑顔を見ると、少し誇らしい気持ちになった。
自分が彼女の助けになれたことが、嬉しかったのかもしれない。
「ありがとう、悠太。これでやっと、理想の写真が撮れるわ」
彼女の満足そうな声を聞きながら、俺は次の言葉を思わず口にしてしまった。
「バイト料、結構良かったから、次もあったらやるよ」
七海は驚いた表情を一瞬見せた後、またあの笑顔を浮かべた。
「ほんと?じゃあ、またお願いね」
その日、俺は自分が少し成長したような気がした。
それと同時に、七海と過ごす時間が、少しずつ特別なものになっていく予感がした。

写真撮るときって、自分だと表情とか構図って分かりづらいんですよね。
撮る側に意図があれば指示もできますが、一人だとかなりマンネリに。
可愛い写真を撮りたいなら、パートナーがいても良いかも?
もちろん女装趣味やロリータ趣味を暴露しても良い人を選んてください。

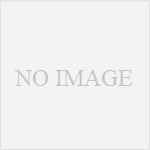
コメント