
大学生の翔太は、友達に連れられて夜のバーに訪れることになった。
普段なら行かないような場所だが、特別なイベントがあるということで、なんとなく参加することにした。
しかし、酒に慣れていない翔太は、カウンター席でソフトドリンクを注文し、静かに過ごしていた。
「いらっしゃいませ。何にいたしましょう?」と美しいママが笑顔で話しかける。
彼女の名は沙織。夜の街で有名なバーを営む、少し強気で優しい大人の女性だ。
しかし、突然目の前が暗転し、翔太は意識を失った。
次に目を覚ましたとき、翔太は見知らぬ場所にいた。
そして鏡を見ると、自分が「沙織」になっていることに気づく。「えぇ!?何で俺がこんな姿に!?」
同時に、沙織の方も、鏡の前で自分の姿が若い大学生になっていることに驚いていた。「まさか、こんなことが本当に起こるなんてね…」
沙織は、翔太の若い男の身体を見下ろしながら、何とか状況を把握しようとした。
入れ替わった原因は分からないが、今夜のバーを営業しなければならないことは明白だった。
沙織は翔太に言った。「仕方ないわ。私はあなたの身体でバイトとして店を回すから、あなたは私の代わりにカウンターに立って、お客さんの相手をお願いね。」
翔太は不安そうな顔をしながら、「え、俺、お酒作れないよ!?」と訴えたが、沙織は軽く肩をすくめ、「大丈夫、あたしも男の体でバーを仕切るのは初めてよ。でも、やるしかないわ。」と言って店の裏に向かった。
カウンターに立った沙織(翔太)は、困惑したまま客を迎えることになった。
最初の客が席につくと、すぐに「おすすめのカクテルは何?」と聞かれたが、翔太は全く答えられない。
無理にカクテルを作っても、バレバレで恥をかくだけだ。
「す、すみません。今日は特別な日でして、カクテルは…うーん、相談に乗ることなら得意です!」と苦し紛れに言ってみた。
客は驚いた表情を見せたが、「悩み相談?それも悪くないな」と興味を示した。
こうして、翔太はバーテンダーではなく「相談役」としてその場を乗り切ることに成功した。
「最近仕事がうまくいかなくてさ…」
「そっか、大変なんだね。でも、焦らない方がいいと思うよ。少しずつ進めばいいんじゃないかな。」
いつもならママらしい深い言葉を期待されるが、翔太は自分なりに真剣に答えた。
それが逆に新鮮だったのか、客は満足して帰っていった。
一方、沙織(翔太の体)は、初めての男の体でのバイトに奮闘していた。
バーテンダーとしての経験が豊富な彼女だが、翔太の体は自分とは全く違う筋肉と動きで、最初はぎこちなくなってしまう。
「お待たせしました、ビールです!」と、ぎこちない笑顔で客に提供するが、客たちは逆にその不器用さを微笑ましく感じ、翔太になった沙織を応援していた。
「いやー、なんかその姿勢、初々しいね!」
「新人さん?なんだか新鮮ね!」と、店は思わぬ盛り上がりを見せることに。
沙織は心の中で「ふぅ、男の体ってこんなに大変なのね…」と思いつつも、意外とバイトを楽しみ始めていた。
夜も更け、バーの営業が終わる頃、翔太(沙織の体)と沙織(翔太の体)はカウンターで向かい合っていた。
疲労感が体に重くのしかかってきたが、互いに笑顔を見せ合う。
「今日はお疲れ様ね」と、沙織は翔太の体で深く息をついた。
「俺、もうクタクタだよ…これで一人前のバーテンダーって言えるのかな?」と、翔太は沙織の体で冗談を飛ばした。
「悩み相談バーテンダーも、悪くなかったんじゃない?」と、沙織は微笑んだ。
そのまま二人はしばらく話を続け、意外にも入れ替わったお互いの体験について共感し合った。
だが、次第に疲れがピークに達し、ついにはお店のソファに並んで横になることにした。
「まあ、今夜はもう何も考えずに寝ましょう。明日にはまた元に戻ってるかもしれないわ。」
「そうだな…」翔太は、沙織の体で深い息をつき、すぐに眠りに落ちた。
沙織も同じように、翔太の若い体で眠りについた。
朝の光が薄暗いバーの窓から差し込んだ頃、翔太はゆっくりと目を覚ました。
昨夜の疲れはまだ残っていたが、何かが違う。
身体が軽い…自分の感覚に戻っているような気がした。
「え…俺、戻ってる!?」
驚きの声を上げて身体を確認すると、元の自分の姿に戻っていることがわかった。
沙織もソファから起き上がり、自分の体に戻っていることに気づいた。
「戻ったのね、私たち…」沙織は少し驚きながらも、安堵の表情を浮かべた。
二人は顔を見合わせ、しばらくの沈黙の後、ほっとしたように笑い合った。
「やっぱり、ママの仕事は俺には無理だな。でも、少しだけお客さんの気持ちがわかった気がするよ。」と翔太が言うと、沙織は軽く頷いた。
「あなたもよく頑張ったわ。お酒を作れないなら、悩み相談に徹するというアイデアはなかなか良かったと思う。」
「そう言ってもらえると、ちょっと自信がつくかもな。」翔太は照れ笑いを浮かべた。
「でも、もう一度入れ替わるのはごめんね。やっぱり私は自分の体が一番よ。」と沙織は冗談混じりに言いながら立ち上がり、いつものバーママの姿に戻った。
「俺も、自分の生活が恋しいよ。」翔太も立ち上がり、二人はバーの外に出る準備を始めた。
その日の朝、二人はお互いを一段と理解し合い、特別な一夜を共有したことを心に刻んだ。
そして、普段通りの生活に戻るべく、それぞれの日常へと歩き出したのだった。

いきなりお酒を作る立場なんて、知識や技術の観点から無理ですね。
バーテンダーさんのような深い話も難しいでしょうし。
でも、案外相談受ける側は聞いて頷くだけでいいのかも?
する側は大体聞いてもらいたいだけだし。という妄想です。

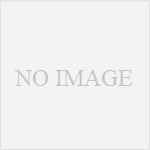
コメント