
佐倉健人、30歳。システムエンジニア。
オフィスビルのガラスに映る自分は、いつも疲れ切って冴えない、ただの「佐倉健人」だった。
デスクワークの合間、彼の頭の中を占めるのは、仕事のタスクではなく、ある種の強烈なフェティシズムだ。
彼の人生を彩る唯一の情熱――それはセーラー服である。
夜、誰もいない部屋で、健人はインターネットで集めた制服カタログを、まるで宗教画でも眺めるかのように広げる。
紺の生地に引かれた三本の白いライン。
胸元で結ばれた赤いスカーフ。
その完璧な幾何学的な美しさに、常に心臓を締め付けられるような、甘美な焦燥感を覚えた。
「いつか……」
それは、今まで決して口に出すことのなかった、最も秘めたる願いだった。
「見る」だけでは、もう物足りない。
この憧れの衣装を、自分自身が纏いたい。
その夜、健人は決壊したように震える指で検索窓に文字を打ち込んだ。
「女装 メイク スタジオ 社会人」
いくつか表示されたサイトの中で、彼は一軒の店に強く惹かれた。
過度なアダルトさもなく、清潔感のあるデザイン。
まるで美容院かエステサロンのような、洗練されたウェブサイトだった。
その店の名は「スタジオ・ヴィーナス」。
迷う時間は、もはや残されていなかった。
どうせ誰にも見られない。
これは、自分だけの、一生に一度の秘密の冒険だ。
彼は、震える指で予約フォームにアクセスし、「初めての体験」「セーラー服希望」と記入した。
予約の日、健人は指定された住所へと向かった。
雑居ビルの二階。エレベーターを降りると、そこだけ空気が違う気がした。
ドアの向こうから、別の世界が始まっているような、そんな緊張感。
「よし、深呼吸だ。佐倉健人。ただの趣味だ。何も恥ずかしいことはない」
心の中で必死に自分を励まし、彼は恐る恐るノックをした。
「はーい、どうぞ」
中から聞こえたのは、優しく明るい、女性の声だった。
「あの、佐倉で予約した者ですが……」
ドアを開けると、そこはモノトーンを基調とした、モダンで落ち着いた空間だった。
そして、出迎えてくれたのは、茶色の髪を軽やかにまとめた、細身の女性。
彼女は健人の緊張を一瞬で見抜いたようだった。
「お待ちしておりました、佐倉さま。私が本日の担当をさせていただきます、ユキと申します」
ユキはにっこり微笑んだ。
その笑顔は、健人が持っていた「女装の店」に対する漠然とした怪しさを一瞬で払拭した。
「ま、まずは、こちらでお掛けください。今日はありがとうございます」
健人は勧められるままソファに座った。
店内には心地よいヒーリングミュージックが流れている。
「佐倉さまは、セーラー服をご希望とのことでしたね。今日は、下着から制服、ウィッグまですべてこちらでご用意いたしますが、何かご持参されたものはありますか?」
ユキは慣れた口調で尋ねる。
健人はもごもごと言葉を詰まらせた。
「いえ……その、すべて初めてでして……」
「ええ、もちろん大丈夫ですよ!初めての方でも安心していただけるよう、一からサポートさせていただきます」
ユキは優しく言った。
「まずは、この更衣室で『ベース』となる下着を選んでいただきましょうか。サイズは普段着用されているもので大丈夫ですよ」
ユキが差し出したのは、清潔な白いショーツとブラジャーのセットだった。
女性ものの下着を買うこと自体、健人にとっては生まれて初めての経験だ。
頬がカッと熱くなるのを感じた。
「あの……これは、購入するということで……?」
「はい。デリケートなものですから、こちらで使い回しはしておりません。持ち帰りいただいても、もちろんこちらで処分しても構いません。さあ、遠慮なく手に取ってくださいね」
健人はまるで爆弾に触れるかのように、その下着のセットを受け取った。
布の薄さ、レースの繊細さ。
「これから、これを自分の体が身につけるのか」
という事実に、ゾクリとした戦慄が走った。
「では、着替えが終わりましたら、こちらのブースへどうぞ。早速、メイクを始めましょう!」
ユキは健人を更衣室へと促した。
更衣室の扉を閉めた瞬間、健人は深い溜息をついた。
(来てしまった……。もう後戻りはできない)
彼はスーツを脱ぎ、購入したばかりの白い下着を身につけた。
その瞬間、鏡に映った自分の体が、今までとは違う質感を持つように感じられた。
薄い布地の摩擦が、皮膚を通して全身の神経を逆撫でする。
恥ずかしさと、背徳感、そして、ついに憧れの扉を開けたという高揚感。
三つの感情が、まるで電気のように全身を駆け巡った。
着替えを終え、メイクブースに戻ると、ユキはすでにセーラー服とウィッグを用意していた。
「わあ、お似合いです!では、ここからは私にお任せください。佐倉さまの秘めた魅力を、最大限に引き出しますね」
ユキの流れるような手つきで、健人の顔に化粧品が塗られていく。
冷たい感触、匂い、筆の繊細な動き。
瞼に影が落とされ、頬には淡いピンクが乗せられる。
「少し、目を閉じていただけますか」
ユキの声に従い目を閉じると、不安と期待で心臓がドクドクと鳴っているのが聞こえた。
そして、ついに――。
「さあ、目を開けてください」
健人が鏡を見た瞬間、息が止まった。
そこにいたのは、彼の知る「佐倉健人」ではない。
大きな瞳、陶器のような肌、丸みを帯びた輪郭。
女性らしい、優しげな顔立ち。彼は思わず、鏡の中の自分に手を伸ばした。
「すごい……これは……」
「ふふ。では、最後にウィッグを」
ユキが用意したのは、健人の選んだ前髪の厚い茶色のロングストレートだ。
それを被せられた瞬間、顔立ちが完全に女性として完成した。
「佐倉さま。今日からあなたは『紗来(さら)』と名乗りましょう。紗来さん、とても可愛らしいですよ」
鏡の中の「紗来」は、はにかむように微笑んだ。
「では、最後はお待ちかねのセーラー服です」
濃紺の生地。白い三本ライン。赤いスカーフ。
憧れの衣装が目の前に差し出される。
ユキは手際よく着付けを手伝ってくれた。
硬めの生地が肌に触れる。
体にフィットするスカートの感触。
胸元のリボンが結ばれるたびに、健人の心は高鳴った。
完全にセーラー服を纏った紗来の姿が、全身鏡に映し出された。
(これが……俺だ。俺の理想の姿だ)
スカートの裾を指先で触る。
その仕草すら、もう健人ではない。
紗来の、少し自信なさげな仕草だ。
「完璧です、紗来さん。では、次は撮影用のスタジオへ移動しましょう。お写真、たくさん撮りましょうね!」
ユキがスタジオの隅にある階段を指差した。
それは、撮影用のフロアへ続く、急な木造の階段だった。
「あ、はい」
紗来は期待に胸を膨らませ、ウィッグが揺れるのも気にせず、足早に階段を登り始めた。
一歩、二歩……。
すると、後ろからユキさんの、少し緊迫した声が響いた。
「ちょっと待って、紗来さん!」
紗来は驚いて立ち止まり、振り返った。
ユキは階段の下から、真剣な眼差しで紗来を見上げていた。
「階段を登るときは、スカートの内側から必ず生地を抑えてください。そうしないと、後ろからだと、下着が見えてしまいますよ」
「えっ……」
紗来の顔は、一瞬で熱くなった。
憧れのセーラー服を着て、真っ先に「女性としての振る舞い」を指摘されたのだ。
羞恥心と、プロとしての注意に対する恐縮が、一度に押し寄せる。
「ご、ごめんなさい……つい、嬉しくて」
「いいえ、慣れていないのは当然です。でも、制服を着ている限り、そのスカートがどれだけ短いか、いつも意識してください。女性としての振る舞いを忘れないことが、変身を楽しむ秘訣ですよ」
ユキはそう言うと、階段を数段上がり、そっと紗来の手を取り、スカートを軽く抑えるジェスチャーを教えてくれた。
(そうだ、俺は今、スカートを履いているんだ……)
健人として生きてきた30年間、スカートの存在など意識したことはなかった。
だが、セーラー服という衣装は、彼の欲望を満たすだけでなく、「女性として振る舞う」という新たな責任を彼に突きつけてきたのだった。
「ありがとうございます、ユキさん。気をつけます」
紗来は言われた通りにスカートを抑えながら、残りの階段をゆっくりと登り始めた。
一歩一歩が、健人の日常から、紗来の非日常へと踏み出す、確かなステップだった。

やべぇ。インフルエンザにかかったっぽい。


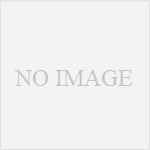

コメント